
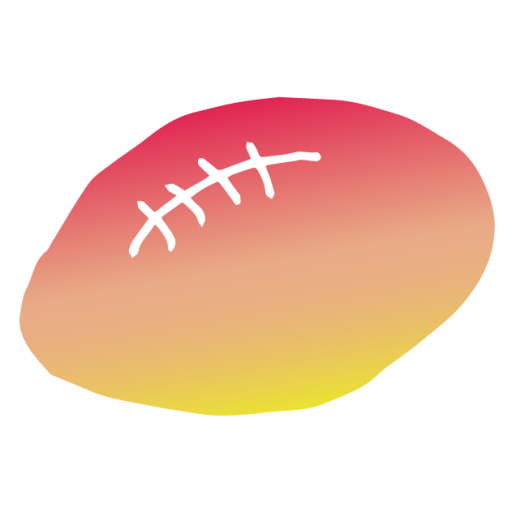 吉岡麻里子さん
吉岡麻里子さん
現在は、横浜市の中学校で体育教師をする吉岡麻里子さん。数年前までは、自身もたまのラグビーを楽しみながら、育成・強化に携わり、ユース世代の日本代表のヘッドコーチを務めていた。日本代表選手として活躍していた吉岡さんがラグビーをはじめたきっかけから、世界で感じたこと、若手世代の育成についてその想いを伺った。
ハングリーであることが広げたもの
「今、ラグビーを続けている女の子はほぼみんな”ごんさん”にお世話になったんです」。
”ごんさん”こと吉岡麻里子さんは、女子ラグビー日本代表として1994年のワールドカップスコットランド大会、2002年ワールドカップスペイン大会に出場し活躍したBK(バックス)の選手。引退後、若手選手の発掘・育成を目的にユースを立ち上げ、ユース日本代表のヘッドコーチを務めた。
そんな吉岡さんがラグビーと出会ったのは日本体育大学に入学後、1年生の秋だった。きっかけは、高校のバスケットボール部の顧問の先生やラグビーをしていたアルバイト先の先輩などが続けて「ラグビーをやったら」と勧めてくれたことだった。
「お前ならラグビーの方が向いている、身体をどんどん当てに行け」。
173センチと身長が高く体格が良い、運動神経も良い、バスケットボールの試合では勢い余ってファールを取られてしまうことも多かった吉岡さんに顧問の先生は冗談半分、本気半分でラグビーを勧めた。そんな周囲の勧めから、当時はまだ大学内でサークルだった女子ラグビーのクラブに入った。

「こんなに人ってハマれるものがあるのかな、ってくらいハマりました(笑)考えたことがグラウンドの上で上手くいくと本当にうれしくて。ああもう、めっちゃ楽しいって思えて」。
指導者がいなかったので、自分たちで練習を考えて試行錯誤した。試合ではどうやってゲームを進めるといいのか、そのゲームメイクを実現させるためにどんな練習が必要か、どんなサインプレイだったら相手は引っかかるのか。大きな声では言えないが、授業を返上する勢いで必死にラグビーのことばかり考えていた。
週3回、大学のグラウンドで練習して、土日はどこかの社会人クラブに混ぜてもらった。日本代表に呼ばれるようになると、自分で遠征費を稼がないと合宿や遠征に行けなかった、ユニフォームも実費。自分たちでデザインし、オーダーしに行ったのを覚えているそう。そんなこんなで空いた時間はほとんど、アルバイトを掛け持ちしていた。

「次にいつチャンスがあるかわからないから、どれだけお金がかかってもいいから行きたかった。スコットランド大会のときは飛行機・ホテル代で100万円。自分で貯めて、少し足りない分を親に頭を下げて支援してもらいました」。
常にハングリーだった。ハングリーであることが吉岡さんの視野を広げ、つながりを作り、吉岡さん自身の人生のベースになっていった。
「代表になって試合に勝てるようになったり、新しい仲間に出会ったり、外国にもお友達ができたり、W杯でトイメンだった選手とコーチとして再会したり、本当ラグビーって楽しい、嬉しいに溢れているよね」。
イギリスへと突き動かした思い
吉岡さんがアルバイトで遠征費を稼いで参加した1994年のW杯スコットランド大会。なんと、試合前日の練習で左鎖骨の骨を折ってしまった。現地入りして2日目のことだった。
「それから全く何もできなくて。チームには帯同しているけど、ただ、ひたすら試合を見る2週間。本当に私は何をしに来たんだって。でも、海外選手との試合を見ながら、世界と戦うには彼女たちのことを知らないといけない、もっと頑張らないと思いました。試合には出てないけど大事なきっかけをお金で買いました(笑)」。

日本は4試合戦って1勝3敗。海外の選手たちと戦うために必要なことは何か、グラウンドの外から吉岡さんは少し俯瞰的な視点で見ていた。技術面はもちろんのこと、海外に渡ってから長丁場の大会を戦うコンディションの作り方など基本的なことが足りていないことを実感した。
大学を卒業してからは、横浜市で産休に入る先生の代理など臨時の職員をしながら、当時、日本体育大学のOGが多く所属していたチーム「フェニックス」(現・東京山九フェニックス)に入り、選手活動を続けた。そして、2001年にイギリスに渡った、スコットランド大会で感じた海外選手を知らなければという想いそのままに吉岡さんを動かしていた。

イギリスに渡ってラグビーの現場に触れて感じたことは、子どもたちがラグビー選手として成長していくための育成プログラムがきちんとあり、カテゴリー間のつなぎがしっかりしているということだった。
「イギリスの子どもたちはミニラグビーから入って成長していきますが、きちんとレールがあるなって感じました。何より良いなと思ったのは、そんな子どもたちをトップレベルの試合や選手がいる場など、きちんとした場面や場所に連れ出し、意図的に良い経験をさせていくんです」。

自分たちで変えていかないと
吉岡さんが代表活動を引退したのは2003年、W杯スペイン大会から帰国してしばらくして31歳の時だった。周囲は、吉岡さんの早い引退宣言に驚いた。
日本として1大会ぶりの出場となった2002年のスペイン大会、十分に準備して臨んだつもりだった。しかし、初戦のスペイン戦に大敗すると、1勝3敗で14位という結果に終わった。吉岡さんは今でも思い出すほど、悔しかったという。
「2002年のW杯が終わった時、海外を知る若い選手を育てないと世界に追いつけない。誰かではなく自分たちで変えていかないと。育成や強化の道に少しでも早くシフトした方がいいと代表活動に見切りをつけたんです」。

吉岡さんと同じように危機感をもった仲間たちが周囲にいて「このままじゃ日本は世界で勝てるようにならない」と話をした。未来の日本の女子ラグビー界のためにプラスになることは何か、そう考えたとき、あと数年の自分の現役生活に掛けるより、未来の子どもたちに長くかかわりたい、指導者になろう、そう思い引退を決めた。
それからすぐに岸田則子さん(元・日本ラグビーフットボール協会女子委員会委員長)と相談して、世界を目指す選手たちを育てる場を作ろうと全国から子どもたちを募ってユースの活動がスタートした。
女子選手のキャリアが中学生で切れてしまうことが課題である日本の女子ラグビー。男の子と一緒にラグビースクールでプレーするのが難しくなる年代をどう繋ぐか、その架け橋を作りたかった。関東から始まったユースの活動は現在、関西、九州と全国に広がっている。

「私がW杯で気が付いた時より早い段階で、”海外選手は大きくて速い”、”世界の舞台では英語が話せた方がいいから勉強しよう”、目指す未来を自分で描くきっかけを与えたい。そんなことを考えて中学1年生の選手をニュージーランドに連れて行ったりしていました」。
選手が自分で気付くことが成長する大きなきっかけになる、それは早ければ早いほどいい。吉岡さんはW杯やイギリスのラグビーの現場で気が付き、大事だと感じたことはできる限り育成の現場で実現していった。
「国際大会やオリンピックの代表選手にユースから成長していった選手たちが選出され、活躍する姿を見ると、やってきてよかったなって思います」。
吉岡さんや仲間たちが継続的に繋いできた活動が強化へと繋がり、日本の女子ラグビーの未来を作っていっている。現場は離れてしまったが可能であればラグビーに携わっていたいという吉岡さん、ラグビーは人を繋ぐ「出会い」を作る存在だという。「切磋琢磨した仲間たちはもちろん、今活躍する若手選手と出会い、混ざり合うチャンスはラグビー以外どこにもなかったです。ラグビーがあったから出会いがあって、色々な経験が出来て。タフすぎる練習もあったけど(笑)それが人生の大きな糧になっています」。

写真・文:WOMEN’S RUGBY COMMUNITY TEAM
HERSTORY: 女子ラグビー選手や女子ラグビーを支える魅力的な彼女(HER)たちが 積み重ねてきたバックグラウンドやその想いをインタビュー、ストーリーとして発信します。


